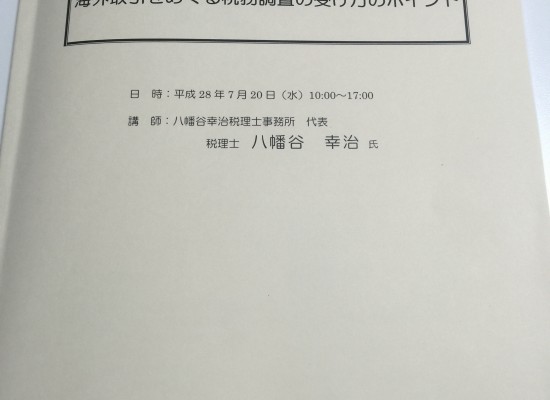商工会議所・日本経営協会様のセミナーに多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。時間の都合上、十分に説明できなかった内容も多々ありますが、まずはトピックや論点に気づいていただくということも大事なことではないかと考えておりますので、できるだけ多くの論点をご紹介するというポリシーで説明しています。社内でお持ちの課題や論点等は、セミナー資料等をご参考に社内でご検討いただいたり、顧問税理士さんと協議していただければと思っております。
また、皆様にご記入いただきましたアンケートはしっかりと確認させていただき、次回以降のセミナーに役立てていきたいと思います。同じ会社の方から複数回参加いただいたり、毎年ご参加いただく方も増えてきていますので、内容を毎回最新の情報にアップデートするとともに、余談のクオリティなども高めていきたいと思っています。
また、国際税務の対応にはある程度の経験値も必要ですので、コンサルティングとしてのご支援依頼も歓迎です。顧問契約としての税務アドバイス以外にも、プロジェクトベースでのご支援(文書化対応や寄附金対応、税務調査対応)や社内セミナーへの講師派遣などもよくご活用いただいておりますので、ご興味等がありましたら、お気軽にお尋ねください。