今年6月に、大阪商工会議所様で半日間、税務セミナーの講師をさせていただくことになりました。
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201504/D11150622011.html
テーマは、2月に日本経営協会様で担当させていただいた「(国際)税務調査における主要論点の実務対応です」の内容のうちエッセンス分をまとめて、国際税務にやや不慣れな皆様で分かりやすいように説明しようと考えています。
元国税調査官としての視点を取り入れ、どのように説明すれば税務調査で効果的な反論ができるのか、ということをテーマにしていますので、国際税務以外の場面でも参考になると思っています。最近、話題になっている国際課税の動きや税務調査でよく争点となるポイント(較差補填金、債務保証等)の論点を追加して説明したいと思っていますので、ご興味がある方はお申込みいただけると嬉しく思います。
作成者別アーカイブ: admin
FAQを追加しました
FAQを追加しました
税務セミナー終了(+サービスメニューの追加)
先日(2月25日)、日本経営協会(大阪)さんにて税務セミナーの講師を担当しました。10~17時まで丸一日をかけて、国際税務の税務調査対応について解説しました。休憩の時間や終了後には活発にご質問等いただき、充実した一日となりました。
前半では、国際税務の概要や寄附金課税の理論的な仕組み、後半にセミナーの理論を実践的な形でご活用いただけるように参加者でペアーになっていただき、簡単な模擬調査のトレーニングを行いました。思っていたよりも皆様活発に議論いただき、またお互いに調査対応についての簡単な情報交換等もあったようです。今後、何らかの方で企業の皆様が気軽に情報交換していただけるような交流の場を設けさせていただくことができれば、とアイデアを練っているところです。
また、セミナーを通じて企業の皆様より以下のようなニーズ終があるこ分かりました。以下のようなサービスが経験に基づいた私の得意分野となりますので、お困りの事項があればよろしければご相談いただけると大変嬉しく思います。
【社内セミナー・勉強会】
税務部・経理部・財務部の方々はもちろんのこと、あまり税務になじみのない海外事業部・経営企画室の担当者向けに、寄附金課税や国際税務の仕組みのセミナー又は税務調査に備えた模擬調査によるトレーニングをいたします。外部の専門家で講師を担当することにより、より実践的で効果のある事前準備をすることが可能です。特に奇抜な対応策があるというわけではなく、企業の皆様が税務調査を怖がらずに、【安心して】調査対応や受け答えをしていただくことを目的としています。
【税務相談(顧問契約)】
社内に国際税務に慣れた税務担当者の方がいらっしゃらないケース又は急に国際取引が増加してきて対応できていないケースについて、サポートをさせていただきます。また、すでに顧問税理士さんと契約されているが国際税務に不慣れなケース等では、既存の税理士さんと協力して、企業の皆様をサポートするようにいたします。単にアドバイスするだけにとどまらず、企業の税務担当者の皆様が数年後には【独力で】国際税務の問題を解決していただけるように、税務の考え方・調べ方等のノウハウ等をアドバイスさせていただき、数年後に自立して独力で解決していただける人材を育成することも目的としています。
【相談対応(税理士さん向け等)】
また、最近、税理士さん・弁護士さん等のご紹介により、国際税務の問題(個人の税務問題等を含め)をスポットで相談対応することが増えてきました。国際税務には普段なじみがなくクライアントからの質問対応に困っている場合等には、後方から先生方のバックアップを喜んでさせていただきます。一般的な内容・スポットのご相談であれば、時間単価(タイムチャージ)でのご相談も対応いたしますので、よろしければご相談ください。
よろしくお願いします。
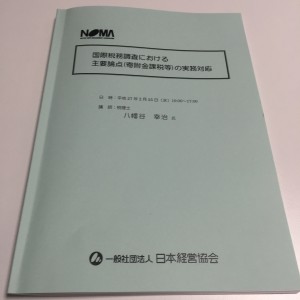
セミナー参加(相互協議の状況、国際税務研究会)
先日、税務研究会(国際)さんの研修で、「最近の相互協議の状況について(アジア諸国)」のセミナーに参加しました。講師は、国税庁相互協議室の方です。
参加して感じたのは、役所の方が講師をされる研修は全般的に資料の読み上げに留まってしまうケースが多々あり、あまり内容に期待を持てないことが多いのですが、今回の研修はそうではありませんでした。
相互協議というのは、国際税務に関する二重課税を排除するための手法で、国どうしが課税権の配分を国どうしが話合いながら決定する手続きとなります。たとえば、日本の国税庁は企業の申し出に従い、課税を受けた(受ける)他の国の国税機関と協議をすることになります。したがって、通常の税務調査と異なり、企業と国税庁(日本)が協力し合いながら、他の国と折衝を行う側面があります。したがって国税庁のスタンスも、税務調査と異なり、企業に協力的なスタンスとなっており、今回のセミナーでもより実務的な話を分かりやすく説明しようとされていたことが印象に残りました。
アジア諸国と折衝を行い両者が納得できる水準で決定を求めることは、相手国の慣習・文化等を考えると非常に困難なことと安易に想像がつきますが、日本の課税権を守るためにも、相互協議室の皆様にはぜひ頑張っていただきたいと思っております。
新年ご挨拶
皆様、あけましておめでとうございます。
本年は、セミナー活動・執筆活動・学会活動を中心にまずはアカデミックな分野に注力していきたいと思います。また、国際課税の世界ではBEPSを中心に激動が予想されるところですが、企業の皆様のお役に立てるようにある取り組みを始めようと計画中です。
本年が、皆様にとって良い一年になりますように。
八幡谷 幸治
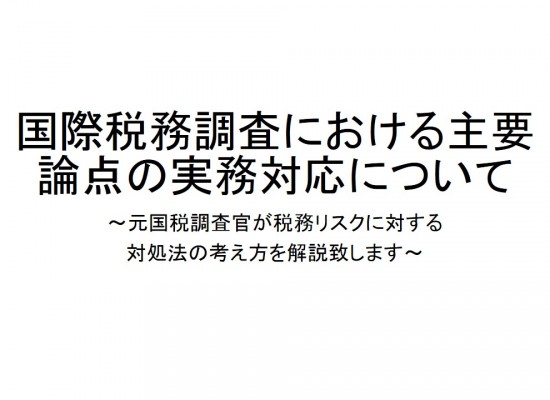
税務セミナーの講師を担当します
来年2月下旬に税務セミナーの講師をさせていただくことになりました。
テーマは、「(国際)税務調査における主要論点の実務対応です」。
丸一日のコースですので、しっかりと準備して、充実したセミナーをさせていただきたいと考えております。 また、元国税調査官としての視点を取り入れ、どのように説明すれば税務調査で効果的な反論ができるのか、ということをテーマにしていますので、国際税務以外の場面でも参考になると思っています。
関西人らしく、笑い(小ネタ)を仕込んでいき、飽きさせないセミナーにしたいと思います(^^)/。
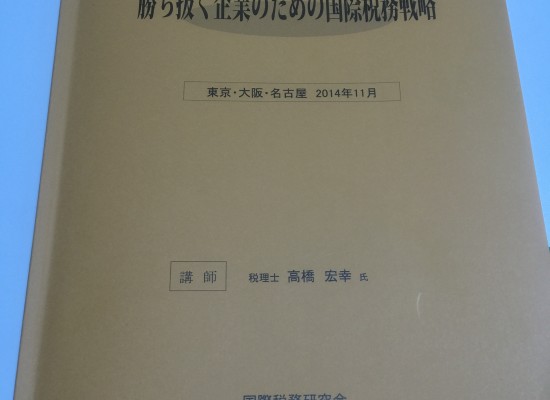
セミナー参加(国際税務戦略、国際税務研究会)
昨日、税務研究会(国際)さんの研修で、国際税務戦略についてのセミナーに参加しました。講師は、高橋宏幸先生です。高橋先生は、国税庁のキャリア採用の方で、国税庁勤務など国際課税の最前線で陣頭指揮を取られた方です。税理士になられてからは大手税理士法人でのご経験や海外での勤務経験もなされているようです。セミナーでは先生のご経験された豊富な経験を基に、国際税務について税務面での制度面の解説に加え、日本企業がこれから進むべき戦略(人事制度、文化の違い等)について、方向性を示唆されていたのが印象的でした。
私も国際税務(戦略)というのは、単に税務のテクニカルな問題だけではなく、企業が進むべき方向性(企業グループ再構築、海外販売戦略、人事制度等)を、たんに税務の面から検討したものであると捉えているため、大局的な見地から企業をサポートする必要があると考えています。つまり税務の有利不利だけで判断するのではなく、営業戦略・人事制度・企業ブランド構築などとともに、税務も一つの重要なパートとして検討する必要があるのではないかと思っています。例えば、企業の税務戦略をご担当される部長クラスの方々には、会計税務の実務的な知識のみならず、役員クラスの見識・大局観が今後求められていると思います。そのような方々から直接アドバイスを求められる税理士は、当然税務の知識のみならず、常識の範囲内でざまざまな見識を深めておく必要があると考えています。
また、もう一つ印象的だったのが最後の税務調査対応のパートで、国税調査官が置かれている現状について熱く解説されていたのが、印象的でした。私も以前から、国税調査官が税務調査で成績を上げるために必死になって厳しい調査を行うマインド(モチベーション)はどこからくるのだろうと、疑問に思っていました。先生がおっしゃていた「公務員であるため給与等待遇には大きな差がつかないので、優秀な人に頑張ってもらうためには、昇進等で差をつける必要がある。そのため、目に見える形で成績が出る税務調査で、各調査官が頑張るモチベーションが生まれているのではないか」という示唆は、なるほどと思いました。
最後に、国税庁等でご活躍されていた諸先輩が民間でも活躍されているのを拝見して、嬉しく思いました。頑張る人はどこに行っても頑張るので、私自身も諸先輩や同期・後輩の皆さんに恥じぬよう頑張っていきたいと、改めて思いました。
法人税の調査事績(発表報道より)
今月、大阪国税局より法人調査事績の発表がありました。特徴的なのは、実地調査件数が前年度対比約90%でということで、調査件数の減少が見られていることです。これは改正国税通則法の影響で、調査手続きの厳密化等により内部手続きが増加したことによる影響があるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/osaka/kohyo/press/hodo/h26/chosa_jiseki/01.htm
ただ国税当局としても税務調査がゆるくなったという印象を持たれることは、望んでいないと思われますので、今事務年度以降、税務調査の件数が通常どおりに戻っていくものと予想されます。実際に、本年7月以降活発に調査が行われている様子がうかがえます。
また、法人税の非違があったのは調査件数のうちの約7割ということで、調査があれば7割はなんらかの修正申告が発生していることになります(3割のうちには、他の税目「消費税・源泉所得税・印紙税」の非違がある場合も含まれます。)。
以前、調査実務の経験をしていた者からの感想とすると、対前年の数値等にこだわらず「悪質な納税者に対しては厳正な調査を、きっちりとコンプライアンスの意識が高い納税者に対しては指導を中心とした穏やかな税務調査を行う」のが、国民感情に合致する(社会から期待されている)のではないかと思います。
更正割合等の係数にこだわり、安易な期間損益(売上繰延や棚卸計上漏れ)で税務調査を終わらせるのではなく、やるべきことをきっちりと行うのが税務調査官の務めではないかと考えております。
セミナー参加(中国投資、国際税務研究会)
昨日は、税務研究会(国際)さんの研修で、中国投資・コスト回収のセミナーに参加しました。講師は、PWCの梁瀬先生です。いつもよりは少し少ないかもしれませんが、70~80名の参加者がいらっしゃいました。
私の経験上、在阪企業の海外進出は、中国だとすっかり生産活動等が安定してきてはいるが、逆に人件費等が高騰してきたり、日中間の情勢が不安定だったりしているので、別の第三国への進出に変わってきているように把握しています。以前から人気のあるタイの他、近年はベトナムへの進出が相次いでいました。ベトナムに関しては少し意外な気もしますが、まだまだ発展途上の要素が多く、税務執行も不安定・不完全な部分はありますが、人件費の低さ・親日的なところが日系企業にとっては魅力的ではないでしょうか。
セミナーに戻りますと、中国税務の難しさはやはり執行上の不安定さ(法律・規定どおり)に執行がされないケースがあるという点でしょうか。例えば、税務上の一定の処理を事前に完了しておかないと日本への送金が許可されないということが特徴的です。このあたりしたたかといいますか、さずが三千年の国の知恵というか、日本も見習うべき点はあるのでは。例えば、一時期外資系のファンドが不良債権処理で大きな利益を上げたものの、日本で税金を負担することなく海外に資金を逃がしてしまったことがありました。その当時の税制では課税できず、後に税制改正で整備された経緯があります。このあたりも送金処理のところで手をうっていれば、もっと早く税制改正等が進んだ可能性もあるのではないかと思います。儲けた方々にきっちりと税金を負担していただくのが、税法の原則です。(もちろん海外からの投資により、地価等の回復が早く進んだという面はありますので、日本国としてメリットは受けていると思いますが。)
中国税務の動向で注目すべき点は、2014年7月に中国当局から出された通達で、外資企業のサービスフィー及びロイヤリティに関する状況調査をするように指示が出ていることです。期間は2004年から2013年の10年間で、例えば海外のタックスヘイブン国へ支払っている場合や経済的実質が不明確な場合、状況調査にとどまらず、否認される可能性もあるようです。
(参考) http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-international-china-hong-kong/china-jun-2014.jhtml
セミナーを通して受けた感想は、セミナーの中では基本的には日本では法律どおりに税務執行が行われるが、中国では調査官のさじかげんで執行が決まってしまうため注意を要するといった論調でした。もちろん対比論でいうとそのような指摘も正しいとは思いますが、日本の税務執行が本当に法律どおりに執行されているかどうかという点については、疑問に感じています。民間で実務経験のある税理士さんは皆さん気づいていることですが、建前は法律・通達どおりの執行ということになっておりますが、現実は異なる点が結構あります。このあたりをどう把握して、日常の税務処理を進めていくことができるかが、税務担当者及びそれをサポートする税理士の腕の見せどころと思います。
サービスメニュー追加
その他サービスに、(期間限定、無料)税務図書コンシェルジュサービスを追加しました。
専門分野は国際税務・税務調査対応に思い切って絞り込む一方、サービスの提供方法は「よろずや」方式でいろいろなコンテンツ・手法を検討しています。